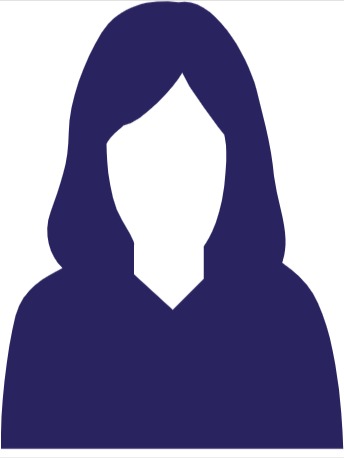
- 子どもの寝かしつけがうまくいかなくてしんどい。
- 寝ぐずりや夜泣きの泣き声を聞くと責められているようで辛い。
- 寝つきをよくする工夫があれば知りたい。
そんな方には「ママと赤ちゃんのぐっすり本」がおすすめです。
\ネントレ本20冊以上読んだカカのおすすめ/
特に年齢・月齢別スケジュールはとても役に立ちます。

この本を参考に生活スケジュールを見直しただけで寝つきが良くなって夜泣きが減ったという声もたくさんあるんですよ。
赤ちゃんが夜泣きをするとママも寝不足になりがち。ゆっくり本を読む時間なんてありませんよね。
でも「ママと赤ちゃんのぐっすり本」はポイントがわかりやすく書かれているので、必要な所を読むだけでOK。
忙しい育児の合間でもササッとチェックできるので安心です。
この記事では、寝不足と育児で毎日頑張っている人のために「ママと赤ちゃんのぐっすり本」の読むべきポイントを簡潔に紹介します。
- 子どもの活動限界時間を知ろう(16~18ページ)
- 睡眠の土台について知ろう(26~32ページ)
- 月齢別生活スケジュール(90~131ページ)
この記事を読めば、我が子の夜泣きに安心して対応するための「ママと赤ちゃんのぐっすり本」の使いこなし方がわかるようになりますよ。

子どもにピッタリなスケジュールや夜泣きの問題は成長と共に変化するので、手元に置いておくと安心な1冊です。
「ママと赤ちゃんのぐっすり本」最優先で読むべきポイント
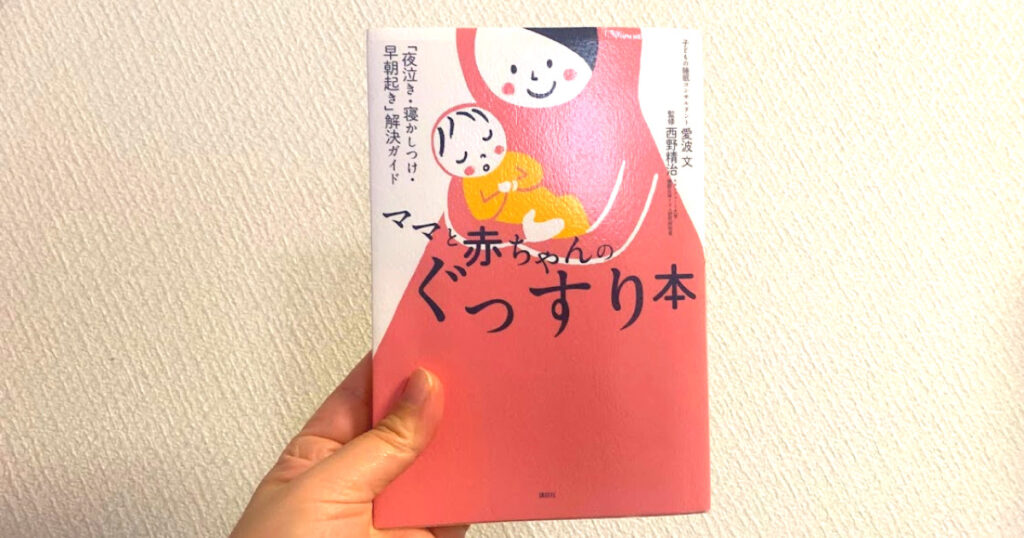
- 子どもの活動限界時間を知ろう
- 睡眠の土台について知ろう
- 月齢別生活スケジュール
夜泣きで余裕のない方に最優先で読んで欲しいのはこの3つだけ。それぞれ説明していきます。

全体的にわかりやすくて勉強になる本なのですが、いきなり全部読むのがしんどい時はこの3つをとりあえず読んでおけばOKです。
子どもの活動限界時間を知ろう(16~18ページ)
「活動限界時間」とはその子が元気で起き続けていられる時間のこと。
スムーズに寝かしつけるためには、この時間をすぎないように意識して寝かしつけを開始することがポイントです。
活動限界時間を過ぎると、以下のようなデメリットがあります。
- 疲れすぎのため寝付きにくくなる
- ぐずりやすくなる
- 寝落ちしても夜泣きや早朝起きが増える
逆に、活動限界時間を意識して寝かしつけてることで、スムーズに寝入ることができ、起きてからもご機嫌で遊ぶことができるというメリットがあります。

「ママと赤ちゃんのぐっすり本」の16~18ページに簡潔にまとめて書かれているので、まずはそこを読んでみてください。
睡眠の土台について知ろう(26~32ページ)
「ママと赤ちゃんのぐっすり本」で書かれている睡眠の土台は以下の3つ
- 睡眠環境
- 幸福度
- ねんねルーティン
寝かしつけをするうえで睡眠の土台はすごく重要です。睡眠の土台が整っていないと、ネントレの効果が半減してしまうからです。
逆に言うと、ネントレをしなくても睡眠の土台を整えるだけで夜泣きが改善したというケースも多くあります。
ですので、睡眠の土台については最優先で読んでいただきたいところの一つです。
月齢別生活スケジュール(90~131ページ)
「ママと赤ちゃんのぐっすり本」では0ヶ月から5歳までの月齢・年齢別スケジュールの目安がわかりやすく書かれています。
これが育児をするうえでとても参考になりました。
- 各月齢で起こりやすいねんねトラブルの原因
- ねんねトラブルへの対処法
- お昼寝の回数や時間の目安
これらのことが簡潔にわかりやすく書かれており、成長と共にどんどん変わっていく赤ちゃんのねんねトラブルを安心して受け止めることができました。
各月齢・年齢ごとに見開き1ページでコンパクトにまとまっているので、忙しい育児の合間でも負担感なく読むことができました。

赤ちゃんがベストコンディションで過ごせるスケジュールは成長とともに数カ月ごとに変わっていくけど、この本が手元にあることで落ち着いて対応することができました。
【ママと赤ちゃんのぐっすり本】最優先で読むべき所をまとめました

ネントレ本、寝かしつけ本を20冊以上読んだ私のイチオシ「ママと赤ちゃんのぐっすり本」。
忙しい人に最優先で読んで欲しい箇所を3つ紹介しました。
- 子どもの活動限界時間を知ろう(16~18ページ)
- 睡眠の土台について知ろう(26~32ページ)
- 月齢別生活スケジュール(90~131ページ)
寝かしつけやネントレについてきちんと知りたいなら、1冊のまとまった本を読むのが一番効果的で効率的です。
たくさんなる寝かしつけ・ネントレ本の中でも「ママと赤ちゃんのぐっすり本」は重要なポイントがわかりやすくまとまっており、文章もとても読みやすいのでおすすめです。
まずはこの記事で紹介した3つのポイントを優先的に読んで、時間や気持ちに余裕が出てきたら他の箇所も読んでみてくださいね。

ねんねのコツをつかむと育児がもっと楽しくラクになりますよ。
読みやすいマンガタイプもあります。
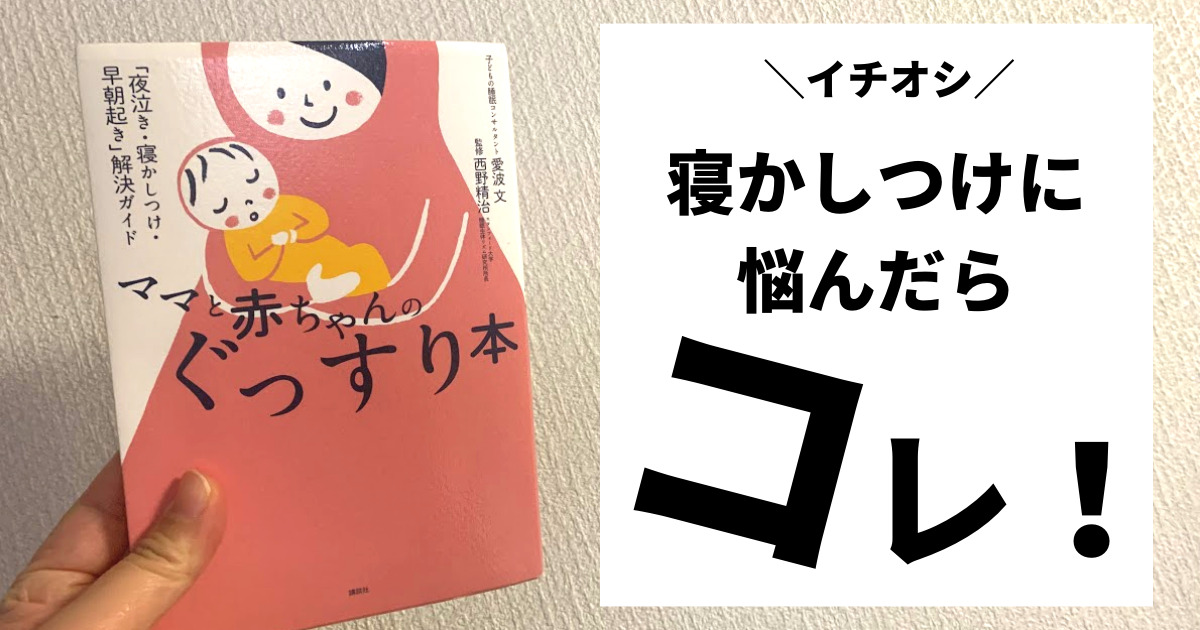


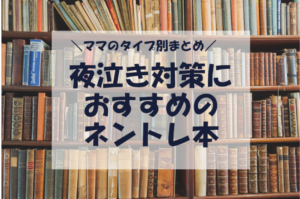
コメント